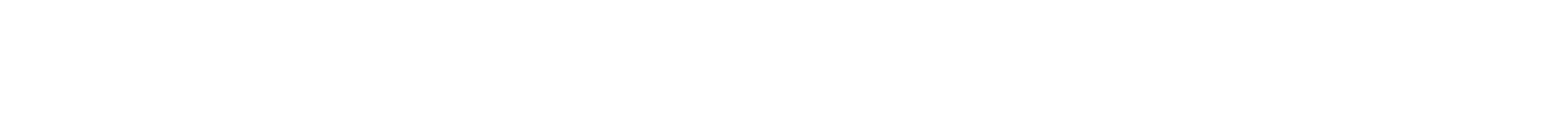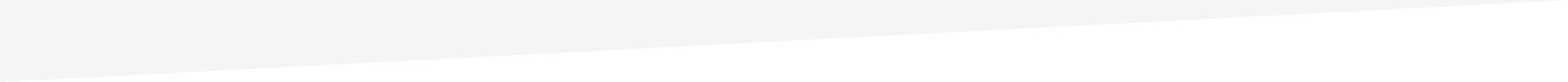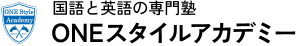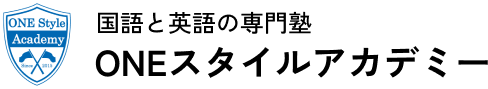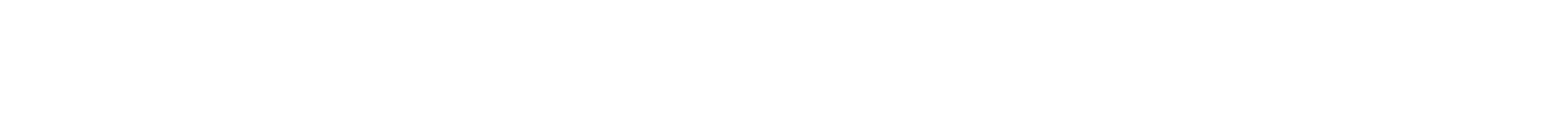
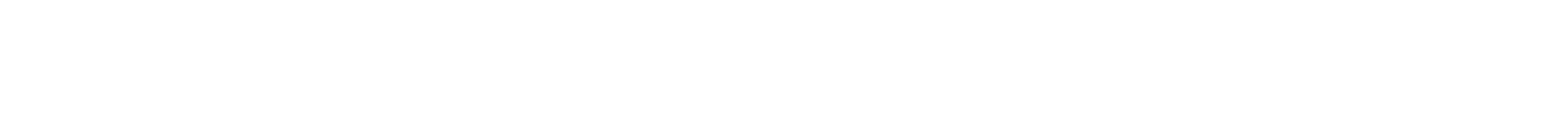
新着情報
2025.10.26
過去問はどう取り組んだらいいのか?始める時期や回数は?
夏休み以降バタついていてなかなか更新できませんでしたが、しばらくぶりのブログです。
今回のテーマは過去問です。
この時期にはすでに受験に向けて、どこの塾・ご家庭でも入試の過去問への取り組みを始めていることと思います。
しかし、過去問の利用の仕方をまちがえてはいけません。
過去問に取り組んで実力が落ちることはないと思いますが、効果のないムダな作業になってしまう可能性はあります。
以下に個人的な考えをまとめておくので、よかったら参考にしてください。
まとめ
注意
以下の情報は基本的に中学受験の生徒を対象としています。科目は国語です。
またあくまでも国語の苦手な生徒のための情報で、大雑把にいって模試の偏差値60以上をキープできる生徒は対象外です。
過去問で実力は伸びない
よく「過去問をやっていくうちに点が取れるようになる」 という指導者の方がいますが、少なくとも国語に関しては的を射た意見だとは思いません。
過去問は実力を伸ばすには不向きです。それは、正しい解答が分からないためです。
なぜ正しい解答が分からないのかというと、ほとんどの「過去問の解答」というものは、入試問題を作った学校が正式に公表したものではないからです。
意外に思われるかもしれませんが、一部のテストや学校を除いて、入試問題の正式な模範解答は公表されていません。一部というのは、公立中学入試の適性検査、公立高校入試、大学入試共通テストなどです。
それらを除いた、私立中学・高校・大学の多くは、模範解答を公表しません。一部の私立学校は解答を公表していますが、ほとんどないのが現状です。公表しない理由は余計なトラブルを避けるためだと類推しますが、本題ではないので割愛します。
では、巷にあふれる過去問の答えは何なのか?というと、それはそれぞれの出版社や塾などが勝手に作ったものです。勝手に、というと語弊があるかもしれませんが、少なくとも答えについては、各学校の許可を得て作られたものではないはずです。
会社によって答えが違う
なぜそのように言えるかというと、出版社や塾によって解答が違うからです。特に国語では、同じ問題でも答えが違うことはよくあります。
例えば、とある中学のとある選択問題について 出版社のA社では解答を「○とカ」 としていますが、B社を見ると「○とオ」などとなっています。
記述問題ではもっと差が激しく、 B社は「○○が●●と思っているかのように見えること。」という解答が、 C社では「△△と過ごすことを◇◇している自分の気持ち。」などとなっています。 内容どころか答え方そのものが違っていて、とても同じ問題の解答とは思えません。(※表現などは変えています)。
模範解答が学校から公表されていたら、このような違いは生まれないはずです。
国語の記述の答えは参考例
勘違いしてほしくないのは、だから出版社も塾もいい加減だ、という話がしたいわけではないということです。
公表されてないのだから、「勝手に」作るしかないんです。各出版社・塾などとその担当者が個人的な感性で答えを作るのだから、バラつきがあるのは当然です。
ただ、英語・数学・理科・社会はほとんどの答えが統一されるのに対し、国語の解答、特に記述問題はバラつきが大きくなります。それは「国語の記述問題に唯一絶対の解答は存在しない」ためなのですが、そこの説明はまた別の記事で記述します。ともかく、解答が統一されないのは仕方ないのです。
では、塾や出版されている過去問の解答がまったく信用できないのかといえば、そんなことはありません。
それなりの専門家が作っているのですからそれを頼りにするのは問題ありません。知識や選択問題・穴埋め抜き出し問題については大体一致するのも事実なので、そこまで神経質になる必要はありません。
記述問題の解答については、あくまでも「参考例」ととらえておきましょう。「そういう答え方もあるよ」という程度のもので、絶対的なものではありません。
当塾で指導する時
ちなみに、私が授業でこのような過去問を指導する時は、
①出版社の示す解答を参考にしながら、
②(それが違うと感じたら)私だったらこんな解答を作る、というのを示したうえで、
③君たちだったらこれくらいの内容を書ければオッケー、という「妥協の答え」を教えます。
記述問題を完璧にしようとすると難しく考えて時間がかかるし、そもそも入試で満点を取る必要はありません。妥協の答えで部分点を狙えれば十分です。
過去問は実力養成には不向き
このように、答えが必ず正しい保証がなく、人によってバラつきがあったのでは参考資料にしかなりません。それでは実力を伸ばす練習として不適切であることが分かると思います。
もっとシンプルに言えば、入試問題というのは「生徒の力を試してふるいにかける」ためのものであって、「生徒を成長させる」 「学びを与える」ためのものではありません。練習で実力を伸ばすにはそれに適した材料があるのは当然で、入試問題はそれには値しないと言ってよいでしょう。
過去問は時間配分や問題形式に慣れるためのツール
では過去問に取り組む意味はないのか?というのかというとそんなことはありません。
過去問は、時間配分と問題の形式に「慣れる」ために利用してください。やっていくうちに問題の形式や時間配分に慣れて、実力を発揮しやすくなります。初回よりも、回数をこなした後の方が得点が増えるのは、慣れるためです。実力そのものが伸びたわけではありません。
確認・分析すべきこと
- 大問の構成と問題の数
- 1問にかけられる時間の確認
- 知識の問題と読解問題の配分
- 記述問題とそれ以外の配分
- 独特な問題の確認(体験に基づいて 段落並び替え 続きを書け・・・など)
確認の例
とある中学の問題を確認すると、このようになります。
- 時間 60分 大問 5題
- 1・2:文章読解問題(論理的文章→文学的文章) 3・4:知識問題 5:新傾向問題
- 手順と時間配分
- 3・4・5→10分 、 1→25分、 2→25分
- 読解問題は各8~10問 。本文を読むのに5分、1問につき2分を基本とする
さすがにこのような分析をご家庭で行うのは難しいと思います。塾で過去問の指導をする際に教えてくれるはずなので、それに従いましょう。
もちろんこのような配分も塾や指導者によって違います。私なりの理由があってこのような配分をすすめていますが、これにも絶対的な基準はありません。
実際の練習手順
上記のような次回配分に沿って、実際に問題を解きます。
時間通りにできるようになったら、25分を20分にするなどして少し時間を短くして練習しておくとよいでしょう。本番よりも厳しい状況に慣れることで、本番で力を発揮しやすくなります。
この時に気を付けてほしいことは、あわててやることになるので正解率は下がってもよい、ということです。というか、過去問に取り組む時は得点は気にしない方がいいです。
理由は先に述べた通りで、「本当の正解が分からない」からです。ついでに言えば、塾などが示す「配点」も公式のものではありません。あくまでも想像で、参考である場合がほとんどです。
得点の上下に一喜一憂するのは絶対にやめましょう。意味がありません。
その他注意点
時間をかけて正解 ではなく、 時間をかけずに不正解 を選ぶくせをつける
近年の入試はとにかく時間との戦いなので、「多少の失点は覚悟でスピードを上げる」という選択をしないと最後まで解ききれません。 十分に間に合うスピードを身につけておくのが理想ですが、今からそれを身につけるのは難しいと思います。
過去問を解きながら、割り切った判断ができるように練習しましょう。
読んでから解く、のが理想ですが・・・
国語のテストは本来、「本文を全て読んでから問題を解く」のが基本ですが、スピードが明らかに間に合わない場合は「本文を読みながら問題を解く」でもよいと思います。
まずは全ての問題を解ききることが第一なので、これはしかたありませんね。 ただし、一部のトップ校の国語の問題にはそのやり方は通用しないことは覚えておいてください。
過去問を始める時期は?何回くらいやればいいのか?
よく聞かれる質問ですね。まず始める時期について。
私は12月くらいでいいと考えます。
実際に塾でもそのように指導していて、当塾の生徒でこの時期(10月後半)に過去問を解いている生徒はおりません。
先に述べたように、時間配分と形式に慣れることが目的なので、回数は必要ありません。何となく世間の常識にとらわれると不安になるかもしれませんが、それで十分です。
よって回数も2回くらいでいいです。多くて3回。理由は同じです。受験校が4つだとすれば、1つに2回で、週1回のペースだと8回で2か月です。第一志望の対策を3回にしても、11月の後半で間に合います。
そこまではずっと生徒のレベルに合わせた基本練習に取り組みます。得点を最大化したいのなら、それが国語においては最適解であると考えています。
知識の問題(暗記)について
知識問題 過去問のついでに、知識の暗記についても言及しておきます。
入試直前のこの時期に漢字語句の暗記にどこまで取り組むべきなのか、悩むご家庭も多いと思います。
結論は以下の通りです。
①漢字については(苦手な人は)基本的にあきらめた方がいいです。量が多すぎます。
どうしても気になる人は、対義語と四字熟語に絞ってください。それだけなら残りの期間でも終わらせることが可能です。
②ことわざ慣用句・故事成語はやる意味があります。
③文法は弱点が限定的であれば意味があります。ただし分かりやすく対策できる指導者が必要です。
本人だけ、保護者では(普通は)対応できないので、指導環境が整わないときはあきらめた方がいいです。
国語の暗記に時間を使わない方がよい
一番気を付けてほしいことは、受験直前の勉強として、基本的に国語の知識の暗記に時間を使ってはいけない、ということです。
「読解問題が苦手だから、とにかく知識の問題で稼ぐしかない!」というのは一見理にかなった考え方に思えますが、小6生のこの時期までにに覚えられなかったことを、この短期間に覚えられるかというとどうでしょうか?がんばることはできるかもしれませんが、習得には時間がかかり、成果につなげるのは難しいでしょう。
しかも、国語の試験では知識の配分は低く、学校のランクにもよりますが10~20%程度です。学習範囲がものすごく広いわりに、取ることのできる点数は少ないのです。コスパが悪いと言わざるを得ません。
こんなことを言うと、せっかくがんばっているのに身もふたもないこと言うな、と思うかもしれませんが、そういう割り切りが必要な時期であることは確かです。
※余談ですが、急にやる気になった・最後に成績が爆伸びした、みたいないわゆる「覚醒」話を真に受けるのはやめましょう。100人に一人の奇跡です。
この時期にやるべきことは理社の暗記と計算!
ただし、何も全てをあきらめろと言っているのではありません。
国語の暗記はコスパが悪いからあきらめるのも一つの手と言っているのであって、他にやるべきことがあると思います。
それは、理科社会の知識の暗記と算数の計算練習です!確実に得点を伸ばすことにつながります。
理社は国語に比べれば知識で対応できる問題が多いし、漢字に比べれば覚える知識の個数が少なく、勉強した成果が得点につながりやすいのは確かです。
算数の計算練習は必須です。短期間でも毎日練習すれば伸ばすことが可能です。計算の正解率が70%の子がそれを90%にできれば、確実に得点を10点以上伸ばせます。
受験の合否は合計得点で決まります。国語が苦手なら、短期間でそこを克服しようとするのではなく、できることに集中した方がいいです。
国語は割り切って大失敗にならないようにしのいで、他で稼ぐことを目標にしてもよいのではないでしょうか。
まとめ
いかがだったでしょうか?参考になる話があれば幸いです。
なお、今回の記事では各学校の傾向対策については触れておりません。それは出し渋ったのではなくて、中学受験にそんな攻略法はないし、あったとしてもそれに頼らない方がよいと考えているためです。
中学受験はその合格自体ではなく、あくまでも今後6年間の学習環境を選ぶことが目的です。 実力で受かることを目指しましょう。理想の追求の話をしているのではなく、現実の話としてお考え下さい。
コツや小手先のテクニックのお陰で受かっても、レベルが合わずに後で苦しむのは本人です。どうか、目先の結果ばかりにとらわれずに、長い目で見てあげていただきたいと思います。
当塾の受験に対する方針は、「受験の結果に失敗はない!受かったところが君にとってちょうどいい学校」としております。
準備不足に対する後悔や残念な結果というものは確かに存在します。悔しいならそれを次に生かせばいいのです。それは中学・高校・大学のどのカテゴリーでも同じです。
それがうまくいくのであれば、過去のことは失敗ではなく経験になります。
どうかみなさんにとって「いい受験」になりますように。
まぐれと奇跡で第1志望大学に受かったもののレベルに違いについていけずにひどい目にあってこんなことなら第1志望に落ちて第2志望クラスの大学に行けばよかったと激しく後悔したことのある 伊藤