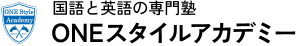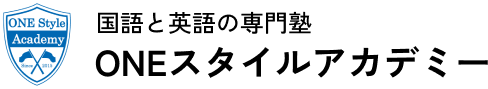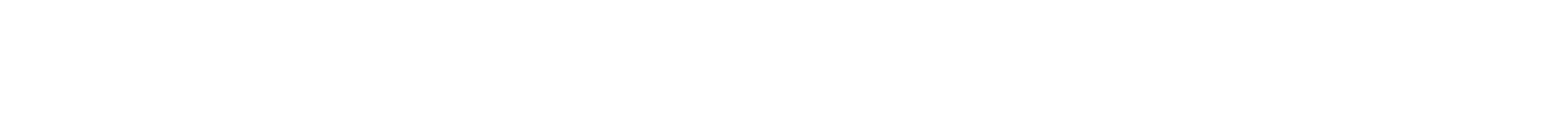
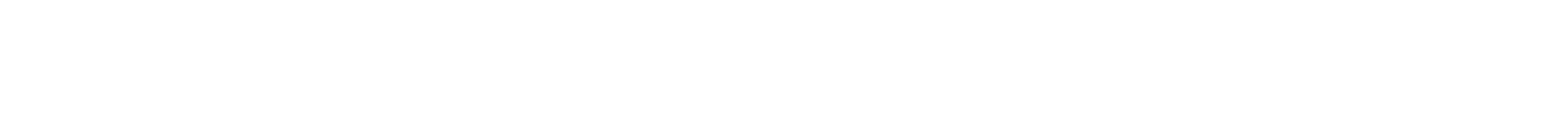
OSAの国語
当塾の国語の授業の特徴を保護者様との
やり取り形式でご説明いたします。
中学受験
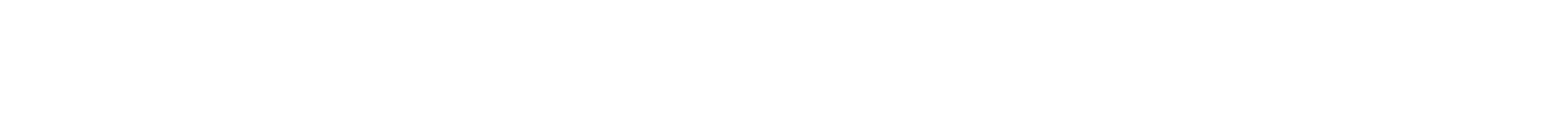
勉強の仕方
子どもが3人いるんですけど、男の子は国語で大苦戦してます。
実際のところ、国語って教えて伸びるものなんですか…?
いきなり核心をついてきましたね!
その質問は「サッカーって教えてうまくなるものなんですか?」というのと同じです。ちゃんと練習すれば伸びます。
とにかくボールをければうまくなるわけではないですよね?ちゃんとした理論にのっとったトレーニングが必要で、体力・ボールをける技術・戦術理解などの要素を組み込んで練習します。
国語も同じで、ひたすら問題集を解く数をこなしても意味はないですね。点を取るために必要な要素があって、それを身につけるためにトレーニングします。
点を取るために必要なことって何ですか?国語でそんなのあまり聞いたことないです。
それは、読解力と問題力(造語)、プラス語彙(言葉の知識量)です。
文章を読む力と問題を解く力、そして漢字や語句の知識ですね。
なんか普通ですね…。
どこの塾でも聞くような話ですよ?
確かに。しかし、どこの塾さんでもいいので先生に「読解力とは何ですか?」と聞いてみてください。
分かりにくかったら「文章を読む時の大事なところってどこですか?」でもいいですよ。
「大事なところ」ってよく聞きますね。
線を引けとか言われました。
読解力とはまさにそれです。
ただ、そこに基準やルールがなかったら意味はないです。またはそのルールが古くて間違っている場合もあります。
「大事なところ」ってどこなのか?どうすればそれが見つかるのか?教えられたことはありますか?
…そういえば、聞いたことないですね。というか、考えたことなかったです。
そこが問題なんです。みんなが当たり前に言っていて、さもそれが攻略法のように言われているけれど、実はそれが根拠がなく、間違っていることすらあるんです。
オセロで「四隅を取れば勝てる」というのと一緒です。
え!?それ違うんですか?
はい。もちろん100%ダメわけではありませんが。少なくともそれだけでは中級者以上には通用しませんね。
四隅を全部取っても負けることはざらにあります。
それが国語の「大事なところに線を引く」ってことなんですね。
そういうことです。個人が何となく、大事だと「思う」ところに線を引いても、それが効果的であるかどうかは分かりません。かえって理解のジャマになる可能性すらあるんですよ。
よほど読書経験が豊富で、感覚感性に優れた生徒はそれでかまいませんが、苦手な生徒はやらない方がいいです。
うちの子は絶対やらない方がよさそうですね…。
苦手だというのであれば、そう思います。
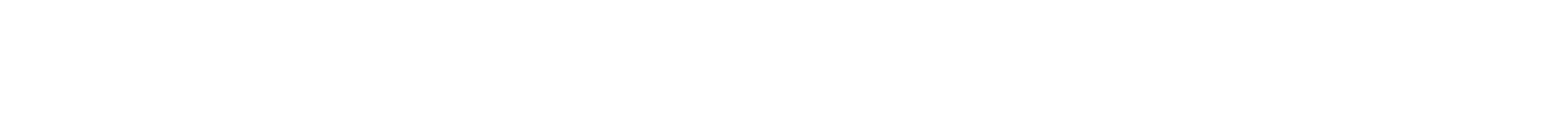
大事なところって?
よく分かりました。
じゃあ、先生の考える「大事なところ」ってどこなんですか?
説明文では「話題と筆者の意見」。
物語文では「場面の展開と人物の行動」です。
なんでそこが大事なんですか?
それが一番本文を速く、正確には短く読むことができ、全体の構成をつかむことにつながりやすくなるからです。
どうすればそこを見つけやすくなるんですか?
決められたルールに基づいて本文にチェックをしながら読みます。
目で見るだけでなく、手を使うことでそこに気づく確率を上げます。
そのチェックってどういうものなんですか?
物語文では人物・時・場所に○をつけ、逆接に△をします。
時と場所の変化を確認したらT マーク、人物の行動と出来事には線を引いて…
ごめんなさい!もういいです。ホントに全部答えていただけるんですね…。
AI みたい。かなり意地悪に質問したつもりなんですけど。
意地悪だったんですか!でもまったく問題ないですよ。
決まりきったルールなので。
すべての作業やチェックには、なぜそうすべきなのか根拠も明確にあります。
明確なルールがあって、論理的なやり方なんだということは分かりました。でもそんな細かいルールをうちの子が覚えれるでしょうか…?
言われたことをまじめにやってくれれば大丈夫ですよ。
ただ、半年~1年は見ていただきたいですね。
結構かかりますね…。
ほとんど読書もしないような生徒を仮定すると、そうなります。
例えばピアノでクラシックの曲をまともに弾こうと思ったら、毎日練習しても2~3年はかかるはずです。
それに比べればハードルは低いんじゃないでしょうか?
そんな簡単なものじゃないですよね。
焦っちゃダメってことですね!?
そうお考えいただけると助かります。コツを学べばどうにかなるというものではないですからね。
学んで、習得し、くせがつき、結果が出るというまでにはそれなりに時間はかかります。当然のことながら個人差もありますからね。それまでに受けてきた指導の「悪影響」も考えられます。
気楽に、気長にお考えください。
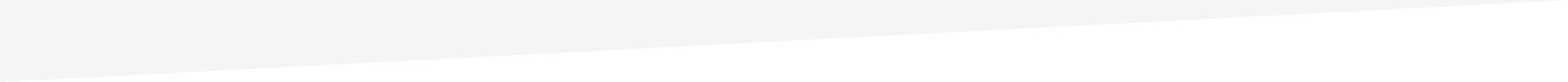
中学受験 中学受験について
中学受験の国語について教えていただけますか? 一番下の子が今小5なんですが本当にできなくって…困ってます。
なるほど。問題点があると思いますが、本文が理解できない・問題の答えが作れない・時間が足りない、どれでしょうか?
全部です。ついでに言葉の知識も足りないと思います。
このレベルから何とかなるんでしょうか? 無理なら無理とおっしゃっていただいても…。
勉強に対して全くやる気がなく、言われたことを全く聞く気がない、という状態でなければ大丈夫ですよ!
ほんとですか?ウチの子は一応やる気はあると思いますよ。他の科目は人並みなので、国語さえ何とかなれば!ってテストのたびにいつも言ってます。
それであればなんとかなりますね。当塾で教えているのは「技術」です。
時間はかかるでしょうが、練習すれば誰でも実行できて、得点アップにもしっかりつながります。
さっきおっしゃっていた、「大事なところ」 とか 「本文にチェックをしながら読む」とかですね?
そうです。そこは本文の読み方(読解力)のポイントですね。
それをベースにしながら、問題の答えの作り方(問題力)も手順を含めて教えます。
選択問題・穴埋め抜き出し問題・記述問題です。
特に選択問題に対する理論には自信があります。
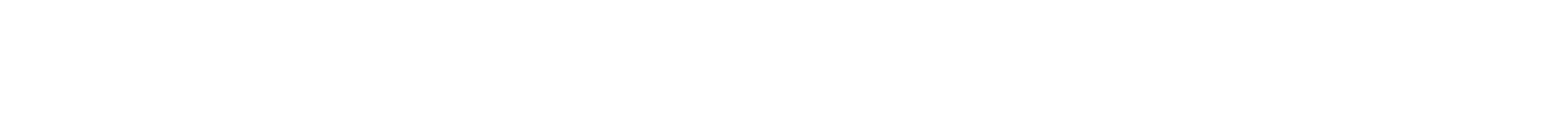
中学受験 選択問題
どんなやり方なんですか?
2つの方法と4つの間違いです。
それだけ?
そんなに難しいことを要求するつもりはありません。このルールをマスターすれば、中学入試どころか大学入試の「共通テスト」でも高得点が狙えます。
知識の問題と「ひっかけ問題」を除いた読解問題に関しては、この技術を完璧に実行できれば満点を取ることも不可能ではありません。
ちなみに…そのルールを具体的に言うとどんなものなんですか?
直接法と消去法の2つの方法。内容・話題・因果・表現の4つの間違いですね。
項目だけでは意味が分からないですよね。そのルールの実際の運用方法を学ぶ必要があります。それはぜひ当塾に学びに来てください。
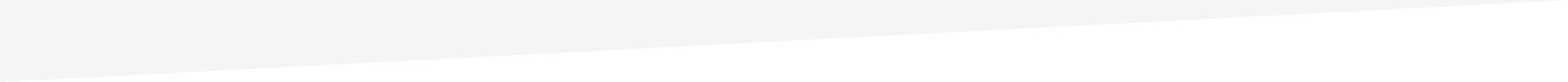
中学受験 記述問題
なるほど、記述問題はどうなんでしょう?ウチの子は答えすら書けないことが多くて…何を書いたらいいのか分からないって嘆いています。
そういう子は多いですね。でも、それもシンプルなルールで対応できますよ。2種類の問題と3つの手順です。
そういう子は、たいてい答えを「自分で考えるもの」だと勘違いしていますね。当塾では答えは「本文から見つけるもの」、そしてそこから「抜き出し」、あとは答えに合うように「整える」という指導を徹底しています。
見つけて、抜き出す、ですか。でもそれだけじゃ対処できない問題もありますよね?
そのレベルの問題は後回しですね。まずは見つけて・抜き出す。
コレで当たる問題を確実に得点できるようになってからです。それが十分にできるようになってから、ようやく高度な表現力を求められる問題にチャレンジできます。
簡単なことから順番に対処できるようにしましょう。いきなりすべてが劇的に変わるわけではありません。
…本当に焦りすぎですね…。
反省しております。
まあまあ。お気になさらず。
みなさん同じようなものですよ。
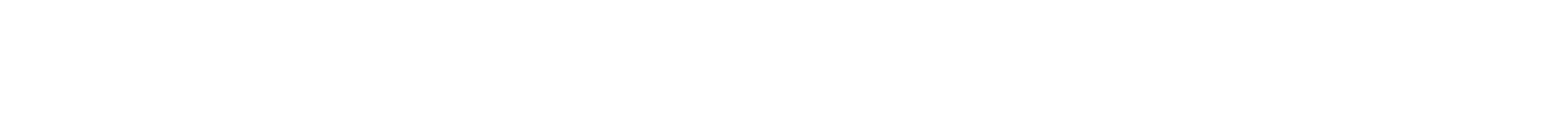
中学受験 授業の進め方
授業の進め方はどんな感じなんですか?
最大の特徴は、初期の段階では「教えながら本文を読み、問題を解く」という点です。
先生と一緒に作業をするんですか?
その通りです。ここまでお話して分かるように、当塾の国語には細かいルールがあるので、口で説明しても伝わるものではありません。
ピアノを教えるときは、楽譜を口と理論だけで説明するのではなく、実際に手で鍵盤を弾いてお手本を見せ、それを真似させながら教えると思います。
それと同じように、まずは一緒にチェックをしながら本文を読み、問題文に線を引き、ヒントの場所を見つけ、答えを作って書く、という一連の流れを教えながら実行させます。
この段階では、読解力・問題力以前の手作業のルールと手順を教えることになります。内容の簡単な問題を使って、本文を「見る→読む→つかむ」ためのくせをつけさせます。
授業でやっていればそれが身につくものなんですか?
授業だけでは不十分なので、宿題でも同じ問題を「白紙」で出して、同じチェックと答えを再現させるようにします。
そこが反復練習ということなんですね? でも同じ問題をやって意味があるんでしょうか…?
素人が生意気言うみたいですみません…。
当然の疑問だと思いますよ。答えが分かっていますからね。
ただ、ここでの目的は答えを当てることではなく、手作業=確認のくせをつけることです。そのための反復練習なので、十分に意味はあります。ルールははっきりしているし、授業でやったプリントがお手本になります。分からなくなったらそれを見て写してきてもいいので、とにかく同じことを再現させます。
結局、面倒くさいとか、時間が足りないからといって確認が甘くなり、見落とし見間違いをしていることが失点の原因なのです。
確認作業の量と質がそろって、かつそこにスピードが加われば、たいていの問題は処理できるようになる、という考え方です。
すごく理にかなってますね。納得できます。
国語の先生の解説って「ここにこう書いてある、だから…」っていう流れですけど、その「ここ」を見つける方法が一番知りたいですよね。
そうなんです!その「ここ」を見つけるためにルールが存在し、まずはそれを手取り足取り教え、手作業の癖をつけ、それを反復して身につけるんです。国語というのは「見つけた者が勝つ」。そういうゲームなんです。
へ~。そう考えれば、ウチの子も受け入れられるかもしれませんね。
そうですね。こういう考え方の方が、今時の子、特に理系タイプの子には受け入れやすいと思います。
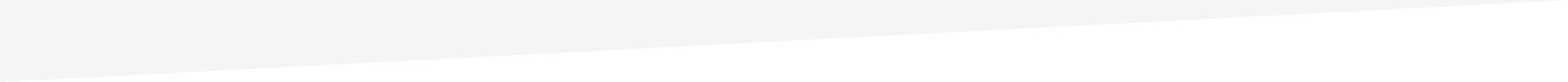
中学受験 反復練習の意味
また、先ほどの答えが分かっていることの反復も、そこが目的です。
というと?
形はどうあれ「当たる=〇がもらえる」ことが重要だということです。
当塾に来るのはほとんどが国語の苦手な子です。読書経験がない、語彙も足りない、そして得点も低いとなると、とにかく自信がありません。
通常の、まず自分でやらせてそれから解説、という手順の授業だと「ほぼダメ出し」の時間になってしまうんです。
ここを見てないから、ここを勘違いしているから、この言葉を知らないから間違える、というダメ出しの連続です。
当たっている子が上で、間違えた子は下です。
集団授業がそのような競争意識をうまく活用しているのは事実だし、こんな程度でへこんでいるようでは受験生としてやっていけない、というのもあながち間違いとはいえません。
ただ、下位に追いやられた子はダメ出しされる中でだんだんと自信を失い、国語が嫌いになります。
そのような子にとっては、「宿題をやってきて、満点がとれる・プリントに○ばっかりがつく」ということもかなり大きな意味のあることなんだと思います。
「そら当たるやろ!」と思いながらも(笑)、「お~満点じゃん」とちょっと認めてあげることは、初期の段階としては重要なことなんです。
そういう気遣いもあるんですね。
それなら安心です!
ありがとうございます。
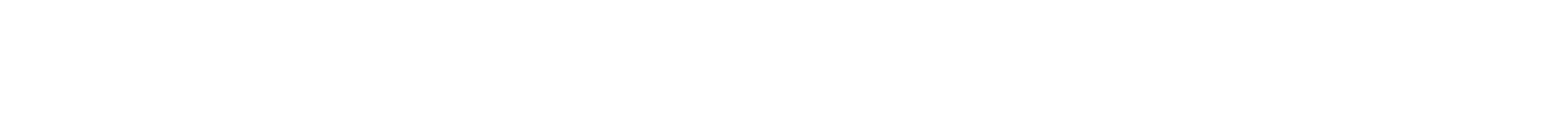
高校受験 高校入試対策
真ん中は中2の女の子なんですが、国語は苦手というほどではないですが、定期テストは取れても模試だと苦戦します。なんででしょう?
校内向けの定期テストの勉強と模試・実力テストの勉強はまったく違うものですね。
前者は暗記科目で、後者は技術科目(※造語。数学なども含む)として考えるべきです。
定期テストができるということは、授業をまじめに受けて、知識の暗記はしっかりできているということです。
模試で点が取れないのは、先ほどの中学受験でもお伝えした、読解力と問題力のどちらかに問題を抱えていると思います。知識には問題はなさそうなので、技術的なことを身につければ点数は上がるでしょう。
おそらくは、先ほどの弟さんよりは短期間で結果が出ると予想します。
じゃあ、そんなに深刻に考える必要はないですか?
そうですね。高校入試に向けて大事なのはまず内申点です。だから定期テストで点を取ることを優先してください。
よほどひどい状態でなければ、本格的に国語の模試、そして公立高校入試対策を始めるのは中3でいいですよ。
ちなみに部活はやってますか?
はい。バスケ部の次期キャプテンだと本人は言ってます。
それは頼もしい!だとすると勉強に集中できるのは中3の夏休み以降でしょうね。それで問題ないと思います。
それで間に合うんでしょうか…?
絶対とは言えませんが、たぶん大丈夫ですよ。あくまでも定期テストの成績が良い=知識の暗記がしっかりできていることが条件ですが。
理由は、シンプルに愛知県の公立高校入試は標準的な内容だからです。
そうなんですか?
英語も基礎的な内容だし、国語もそうです。他の科目をそこまで細かく分析したことはないですが、難しい問題はないです。公立中学生向けのテストですからね。内容・難易度に制限があります。全国的に見ても(たぶん)簡単な方に入ると思います。少なくとも大阪や東京の子からしたらうらやましいでしょうね(笑)。
そんなに違うんですね。
はい。作業量が全然違います。
国語については、上位の私立中学試験の方がはるかに難しいです。
言葉の知識のレベルはさすがに上がりますがそんなに変わらないし、何よりも文章の長さと問題の数、それぞれの問題の難易度が違いすぎます。
公立高校入試は本文も短いし、設問も論理的で解きやすいです。
何よりもすべて選択問題ですからね。先ほど言った選択問題のルールを使えば、読解問題は満点狙いも可能ですよ。大学入試の共通テストで通用するやり方ですからね。
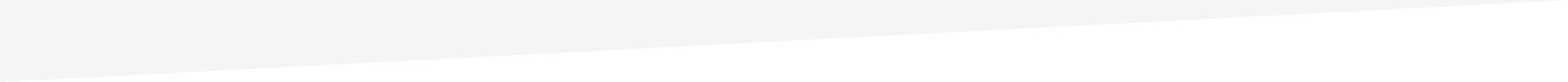
高校受験 高校入試の古文・漢文
それは安心しました。でも高校入試では「古文・漢文」が出るんですよね?すごく難しいと聞きましたが、そちらはさすがに満点狙いはできませんよね…?
できますよ。難しいって、どちらで聞かれたんですか?
名前は出せませんが、どこかの集団塾の先生がそうおっしゃっていたので…。
え、ウソなんですか?
ウソではないんですが…やり方次第です。手順をまちがえるとすごく難しくなり、勉強時間が極端に増える上に普通の中学生ではできません。
じゃあ、違うやり方をすればもっと簡単になるということですか?
はい。名付けて、ジグザグ読みです。
なんか・・・全然すごい方法に聞こえませんね(笑)。それで満点が狙えるんですか?
はい。基本満点で、最低でも1問間違いまでです。
ただし、言われた手順を絶対に守ることと、「やってはいけないこと」を絶対にしないこと、この2点が条件です。
先ほど言った難しいやり方というのは、この「やってはいけないこと」をやってしまうからなんです。
なんですか、そのやってはいけないことっていうのは?
現代語訳です。
古文を現代語訳せずにどうやって内容を理解するんですか?
それが、ジグザグ読みです。ここでは長くなるのでしませんが、いずれブログで公表しますよ。
ブログを読んだだけで実践できるならそれでいいし、無理なら習いに来てください。古文についてのみなら、夏期・冬期の短期講習だけでも効果はあります。
安心しました。それなら高校入試は何とかなりそうですね。
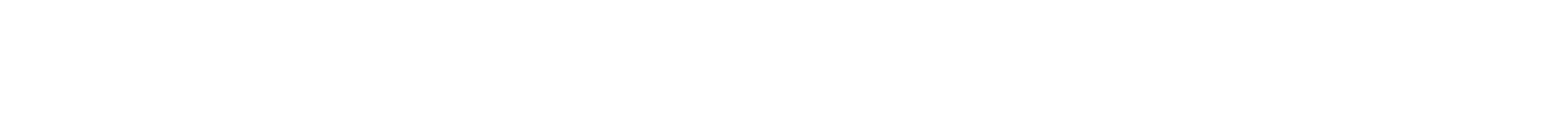
大学受験 共通テスト対策
長男は今高校2年生です。本人は医学部に行くって言うんですけど…。数学理科社会は問題ないのですが、国語英語はとてもそんな成績じゃなくてヤキモキします。
公立高校入試は簡単と言いますけど、共通テストはどうなんですか?
正直に言って簡単ではないです。手順を覚えただけでどうにかなるほど甘くはないですね。でも、これも教えることは技術ですから、練習すれば何とかなりますよ。基本は中学・高校入試対策と一緒です。形式のある程度固定された選択問題なので、対処法はあります。
古文漢文ももっと難しくなるんですよね。それでも満点は狙えるんですか?
さすがに共通テストで満点は難しいですね。理系であれば最大で8割を目指すのが現実的です。医学部受験だとお釣りの来る点数ではありませんが、志望校受験を断念することにはならないはずです。悪くても7割以上はキープしたいところです。
共テ国語の最大の問題点は時間が足りないことです。まともに確認しながら解くと120分くらいかかるのではないでしょうか?実際の試験時間は90分なので、相当なスピードが要求されます。
もう1つの問題は1問の配点が高すぎることです。1つ7点の問題が多いため、各大問5題で1問ずつ間違えただけでも7×5=35点マイナスになり、165/200 点になってしまいます。一つのミスが結果に響く厳しいテストですね。
スピードが要求されて、ミスの許されないテストってことなんですか?なんか絶望的になってきました…。
そこまで深刻に考えなくても大丈夫ですよ。高2の夏で部活は引退なんですよね?それなら何とかなりますよ。
言い忘れてましたが、今国語の偏差値40台ですよ?
…簡単ではないですね。
でも最短で丸1年、長くて1年半かけて、共テの8割を目指すことは可能ですよ。
ただし、一つだけ条件があります。
なんですか?先生の命令には絶対服従ってことはよく言い含めておきますよ。
それはありがたいですね!
そこも大事ですが、条件とは古文漢文の基礎知識です。
古文の単語と文法、漢文の漢字と句法です。ここについて定期テストで暗記を終えていることが成績アップの条件です。もちろん基礎レベルができていれば十分です。
そこは大丈夫そうですね。娘と同じで単純暗記はそこまで苦労しないようです。
なら問題ありません。共テの古文漢文は、最終的に知識の勝負だからです。知識が足りていれば、あとはずっと言っている読解力・問題力のルールと運用の仕方覚えればいいです。
それらのルールには共通する部分が多くあるのですが、論理的文章・文学的文章・資料問題・古文・漢文と、それぞれのジャンルごとに問題慣れするのに時間がかかりますね。だいたい1か月ごとに各ジャンルをローテーションします。1年あれば2周はできるので、あとは苦手分野を中心に演習を重ねて仕上げます。というわけで1年半ですね。
ちなみに、古文漢文の基礎知識の足りない子はどうしたら…?
下の子がそうなりそうで不安です。
その場合はまず暗記の仕方を教えますね。コツだけで何とかなるほど共テは甘くないので、地道な積み重ねを省略することはできません。知識の暗記と問題演習を同時並行で行うことになるので、時間もかかるし本人の負担も増えますね。
見捨てられることはないと分かって安心しました。
そんなことはしません。ただ、そうならないように弟さんは中学受験が終わったら、早い段階で暗記の仕方を見直しましょうね。